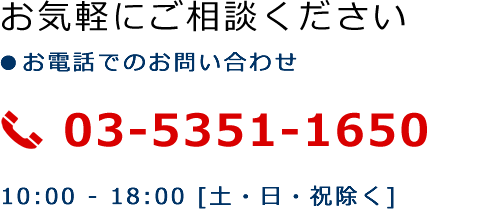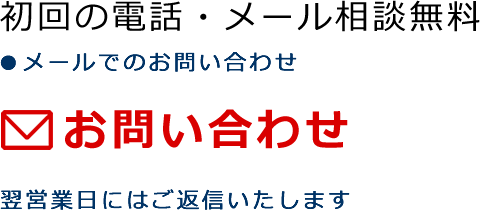事業再生ブログ
事業再生ブログ
【事業再生ブログNO.100】事業改善の問題点は「固定費」か「変動費」なのかの見極めが大事
経営改善を行う上で、売上増強も必要ですが「とにかく売上を上げる」策だけでいいのでしょうか?
「売上は利益の源泉」であるのは事実ですが、売上の中身つまり利益構造(原価構造)を把握するのが一番です。今回は収益体質に転換するための第一歩となる「変動費」「固定費」についてお話しします。
「変動費」と「固定費」の区分ができているのか?
お金が出ていく項目は大きく分けて「変動費」と「固定費」になります。「変動費」は売上に連動するもので、「固定費」は売上が「0」でもかかるものです。よく目にするのは本来「変動費」であるものが「固定費(一般管理費)」の中に混同されており、正確な粗利益が分からなくなっている帳簿です。
例えば「運送費」は売上が「0」であれば発生しないのに「固定費」に入っているものや、「光熱費」でも「本社」の光熱費と「工場」の光熱費が区分されていないものも見かけます。
まずはお金の支出のうち売上に連動するものとしないものとに仕分けることから始めてください。
「変動費」と「売上」の比率を分析してみる
「変動費」の区分が出来たら、次に「売上の分解」を行います。「売上の分解」とは例えば商品・製品ごとなどのカテゴリーで区分することです。ただし、あまり細かく分けすぎると大変な作業になるため、大きな区分けで構いません。
売上の分解ができたら、その売上に対応する変動費を分けます。「仕入材料費」「商品仕入」などのまずは「仕入原価」を見てみます。ここで大事なのは「売上」をひとくくりで見ないでカテゴリー分けすることで、およその「仕入原価」が分かるはずです。「売上・仕入比率」を把握するだけでも大きな前進になります。
製造業の場合に「労務費」の区分をどうするのか?になりますが、正確な管理会計レベルをやるならば「製品製造」ごとの「作業時間・時間単価」「製造機器の使用時間」などを求めていく必要がありますが、中小企業でそこまでやる必要はありませんので、売上比率で分けてもいいでしょう。
「変動費・売上比率」から何を考えていくか
変動費・売上比率を算出することで、各「製品・商品」の比率が過去からどのように推移しているのかを見ます。
例えばA製品の売上は増加傾向にあるものの、「仕入比率」も上昇している場合には「売上が増加するごとに仕入コストが増加」していることになります。
原因としては「材料費高騰だが価格転嫁できていない」「売上ロットが大きくなったので受注先から単価値下げを要求された」などが考えられます。そうなると売上だけを追ってしまうと、製造は忙しくなっているのに、さらにコストが悪化し思ったほどの利益が上げられない「負のスパイラル」に陥ってしまいます。
場合によっては売上を追わないほうが、労働負荷を上げなくて済むかもしれないし、その取引先との取引方針の見直しが必要になるかもしれません。
このように経営改善とは「粗利益」の改善が第一歩になります。お金の支出項目をきちんと「仕分け」することから始めてみてください。