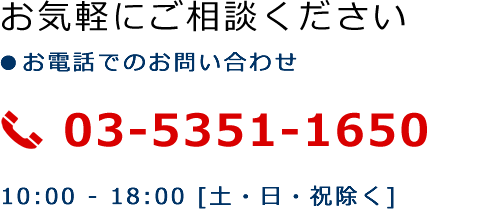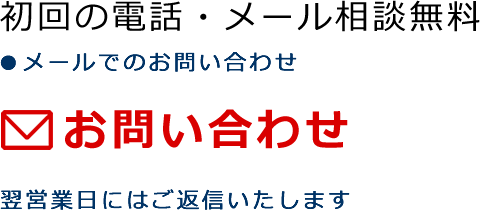銀行融資ブログ
銀行融資ブログ
【銀行融資ブログNO.170】借入金にはかならず「色」がありますが分かりますか?
金融機関から借入をする際に借入申込書に「資金使途」を記載する欄があります。その際に設備を購入する以外のケースはほとんどの方が「運転資金」の欄に〇をしていると思います。
ただし、この「運転資金」という言葉が曲者で、皆さんが知っている「運転資金」とは金融機関の考える「運転資金」とは違うのです。
さらに、借入金には「3つの色」があると言われていますが、この「色分け」がきちんとできてないと資金繰りに大きな影響が出ます。今回はお金の「色」についてお話しします。
「広義の運転資金」と「真の運転資金」の違いとは
何度かこのテーマは話をしておりますが、もう一度「運転資金」の意味をおさらいします。
金融機関の考える「真の運転資金」とは
「売掛金」+「在庫」-「買掛金」にて算出されます。つまり、どんなに赤字で債務超過の企業であっても事業を継続するために必要な資金のことを指します。
在庫をもたなくて売上も現金回収で支払いも現金であれば運転資金は「0」になります。また在庫がなくて売掛金回収が2ヵ月サイトで買掛金の支払も2か月サイトであれば運転資金は「0」になります。
では、世の経営者が考えている「広義の運転資金」と「真の運転資金」の大きな違いはどこにあるのか?
それは「赤字補填資金」のことを見落としていることです。
「コロナ融資」は皆さんよく知っているとは思いますが、「コロナ融資」の本当の資金使途は「運転資金」ではなく「赤字補填資金」です。行動制限がかかり、売上が蒸発してしまったことで、多くの企業は赤字に陥ってしまいましたが、その期間を耐え忍ぶために「コロナ融資」がありました。
さきほどの「真の運転資金」で考えれば、売上が蒸発したことで必要な「真の運転資金」の金額は大きく減少したはずです。
つまり、コロナ融資は「真の運転資金」ではなく「赤字補填の運転資金」になるのです。
お金の色は「3つ」ある
借入金のお金の「色」には以下の「3つの色」に区分されます。
➀「真の運転資金」
➁「設備資金」
➂「赤字補填資金」・「納税・賞与資金」・「M&A資金」などの「特殊資金」
➀「真の運転資金」はさきほどお話しした通りです。➁「設備資金」はモノと紐ついていることから分かりやすいと思います。
難しいのは➂「特殊資金」になりますが、「納税・賞与資金」「M&A資金」も資金使途が明確で分かりやすいと思いますが「赤字補填資金」がなかなか自分自身では分かりにくいと思います。
「赤字補填資金」の大きな特徴は「営業利益が赤字」であるかないかです。営業利益が赤字ということは本業の利益が赤字で、CFがマイナスになっているケースがほとんどです。
また、売上が減少傾向にあれば「真の運転資金」の必要金額は下がるはずですが、それでも全体の借入金額が増え続けていれば「赤字補填資金」の借入が増えていることになります。
「営業利益が赤字」の会社の方は借入が「真の運転資金」なのか「赤字補填資金」なのか見極めが大事です。