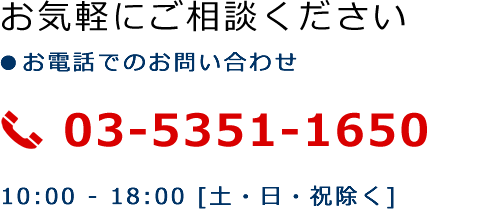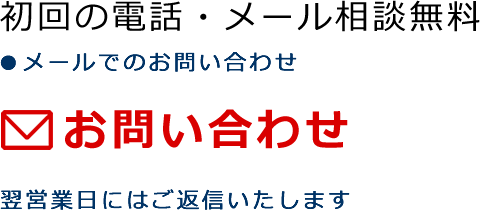銀行融資ブログ
銀行融資ブログ
【銀行融資ブログNO.169】金利上昇時に備えるにはどうしたらよいか?
「金利ある世界」に突入し、徐々に金利が引きあがってきております。これまでのデフレ時代には経験しなかった「金利上昇」時代に入り、債務者は何を考え、何をしないといけないのかについてお話しします。
まずは金利の仕組みを知ること
皆さんが借入する際に提示される金利は以下の「4つの根拠」があって決められています。
➀調達コスト
金融機関にとって皆さんに売る商品は「お金」になります。つまり、「お金」を仕入れるコストになります。
金融機関が「お金」を仕入れる一番の源は「預金」になりますので、お金を仕入れるコストは「預金利息」が一番のコストになります。(もちろん店舗網を維持するコストなども他でかかりますので、金融機関の規模によって変わります)
➁事務コスト
事務コストとは大きなものは「人件費」「システム費」「事務用品費」などになります。メガバンクと地銀・信組等々は人件費の差がありますが、金利に現れる面では大きな差はでません。
➂クレジットコスト
これは債務者ごとの「信用力」によって変わってくるコストになります。財務内容の良い会社ほどコストは低く、赤字が続いている会社であればコストは上がります。決算書に基づく「信用格付」によって変わり、過去の倒産確率に基づいて算出されることから、直近の倒産件数が増えるとそのコストも上がります。
④利益
最後に金融機関の「利益」の部分が加算されます。これは各金融機関によってどのくらいの利ザヤを求めているかによって変わってきます。
金利上昇のリスクを抑えるにはどうしたらよいか
金利上昇のリスクを抑える手段としては、上記の➀~④の構成要素のうち➀と④をいかに考えるかになります。
➀については「短期プライムレート」が低い金融機関と取引できれば金利は抑えられます。基本的にメガバンクは地銀・信金よりも「短期プライムレート」は低いことから、金利面だけで言えば、メガバンクと取引をするほうが金利は低く抑えられます。
ただし、「金利」だけで金融機関を選ぶのは資金繰り戦略上ではリスクが高いので一概には言えません。自社の規模や環境を考慮した取引金融機関の選定が大事です。
➂については、債務者の信用力を上げることに尽きます。信用力を上げるには「利益を創出し自己資本の増強を図る」ことです。
本業の売上増強・粗利改善はもちろんこと、収益力に見合わない「役員報酬の設定」「役員保険の積立」「公私混同な交際費や社用車」など本業にいかに特化したコスパを上げられるかになります。
「ハイブリット」借入はリスク分散のひとつ
よく「固定金利」と「変動金利」のどちらが良いか?と聞かれますが、どちらにもメリットデメリットがあり、どちらが得とも損とも言い切れません。
私は「固定金利」と「変動金利」に分散させて借入することをお勧めしています。例えば50Mの借入をする場合に「固定金利」と「変動金利」分を半々で借入するような感じです。
金利上昇時にはどの程度のペースで金利上昇するかはなかなか予測できないですが、金利を分散させることで双方のデメリットを分散させることができます。是非参考にしてみてください。