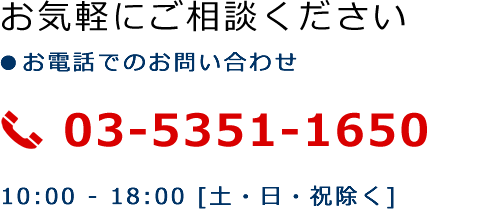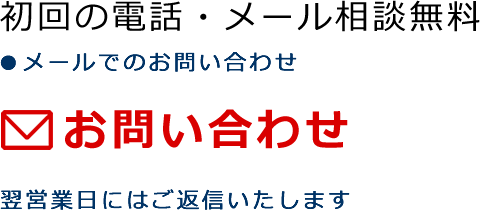銀行融資ブログ
銀行融資ブログ
【銀行融資ブログNO.164】代表者が死去した場合の銀行対応はどうしたらよいか?
経営者の高齢化が問題になっておりますが、不幸にも突然経営者が亡くなるケースがあります。
特に融資取引がある金融機関の取引において、どのような対応をしたらよいのか?についてお話しさせて頂きます。
金融機関への通知は慌ててしなくてもよい
代表者が亡くなった場合、まず優先すべきはご家族の身の回りでいいと思いますし、銀行への通知は落ち着いてからでも構いません。
私の銀行員時代の経験では、亡くなった当日にご連絡を頂くケースもありましたし、葬儀を終えられてからご連絡を頂いたケースなど様々でした。特に役所のように、死後何日以内までに届け出をしないといけないルールはありませんが、長期間お知らせしないことは避けたほうがいいでしょう。
ただし、死後まもなく新たな融資取引を行う(新しい資金を借りる、既往借入金の継続を行う)など新たな契約が発生する場合には、きちんと事実を伝えるべきです。
後継者がいる場合といない場合
金融機関が一番気にするポイントは「事業の継続されるのか否か」になります。
後継者がいる場合は、代表者変更の届出をすれば問題ありません。
ただし「保証人」の扱いについては個社の信用状況や借り入れ状況によって一概には言えませんので、弊社のような専門家にご相談されることをお勧めします。(会社の株式の相続や贈与の問題については税理士にきちんとご相談ください)
保証人については、後継者が保証債務を嫌がるケースもありますので、その点も金融機関とご相談することをお勧めします。(ただ要望が全て通るとは限りません)保証人については「経営者保証ガイドライン」がありますので、まずはこのガイドラインに沿った理論武装が必要です。
後継者がまだ決まっていないが、事業は続けたい場合には、いったん家族でリリーフ的に代表に就任するケースが多いです。例えば旦那さんが経営者の立場で亡くなった場合に、奥様がまずは代表者となり、その後、時間をかけながら後継者を選定することもあります。
後継者がまったく不在の状態になると、金融機関としても契約の相手が不在となると、取引できなくなる状態になりますので「事業清算」でなければ、必ず代表者変更を行う必要があります。
代表者の個人預金口座の確認
代表者が融資取引を行っている金融機関に個人口座を保有していた場合、亡くなった事実を伝えた瞬間に口座は「凍結」されます。その後、ご遺族で相続の内容が決定してはじめて口座の凍結が解除され相続人に引き継がれる手続きになります。(必要な書類等の説明は割愛します) ついては、代表者が健在のうちに「個人預金はどこの金融機関にあるのか」をご家族で把握しておく必要があります。また相続確定前に葬儀代等の払い戻し制度に対応している金融機関もありますので、まずはどの金融機関にいくらあるのか?を把握してください。