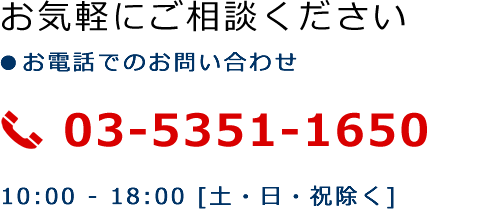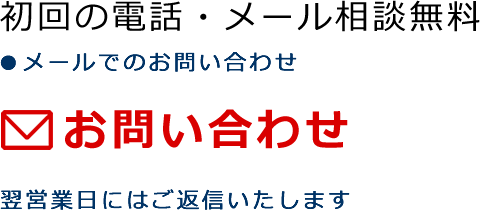銀行融資ブログ
銀行融資ブログ
【銀行融資ブログNO.146】いよいよ貸出金利の引き上げが本格化します
日銀のマイナス金利解除を受けて、銀行が貸出金利の引き上げをいよいよ始めております。直近の新規貸し出しの平均金利はもちろんのこと、既存の貸出金利も約3年ぶりの高水準になっております。
メガバンクだけではなく、地方銀行でも金利引き上げの動きが活発になってきており、企業としてもどのような対応をしたらよいのか?考える時期に来ております。
今回は金利引き上げにいかに備えていくか?についてお話していきます。
金利が上がるのは根拠がきちんとある
銀行の貸出金利を構成する要素は以下の4つが主にあります。
➀調達コスト(銀行が商品である「お金」を仕入れることスト)
➁事務コスト(人件費等のコスト)
➂信用コスト(債務者の信用力に応じたコスト)
④利益
今回のマイナス金利解除に伴う金利引き上げの理由の主たるものは「➀調達コスト」の上昇になります。
皆さんご存知の通り、貸出金の原資で大きなものは「預金」になります。預金金利は既に引き上げられたことから、お金を仕入れるコストが上がり、さらに市場調達が可能な金融機関(銀行間での貸し借りなど)でも調達コストが上がっていることから、企業への「価格転嫁」といえます。
金利引き上げの二番目に大きな理由は「➂信用コスト」の上昇になります。信用コストとは企業の信用格付に応じた引当コストになります。この信用コストは年2回の見直しがありますが、最近では倒産件数の増加に伴い、引当コストが上昇しております。さらに、物価高、人手不足にて企業の業績ダウンに影響が出ており、赤字や売上減少に伴い、企業側でも信用格付けがランクダウンすることで、引当コスト分を転嫁せざるを得ない状況になっています。
つまり、現在の金利引き上げの背景には「仕入れコスト」「信用力コスト」のふたつが大きく作用しているといえます。
複数銀行で常に金利を意識した借入をすること
このような状況下で、企業側としてはどのような対策をしていかなければいけないのか?
〇取引先への適正な価格転嫁を行い、利益率の好転を図る
〇社内の効率化を図り、人員増だけに頼よらないビジネスモデルを構築する
〇取引銀行間でも金利競争意識を働かせることで、銀行の言いなりにならない交渉力を身に着ける
大きくはこの3点が必要になります。
「調達コスト」の引き上げに対しては、無理に拒んでいると銀行側としても「取引解消やむなし」の烙印を押される可能性がありますので、市場金利の引き上げに対してはある程度はやむを得ないと考えるべきです。
それ以上に大切になるのは「信用コストの引き上げ」つまり「企業側の責任で引き上げを言われないようにする」ことです。
金利引き上げの要請を銀行から受けた場合に金利が引き上がる理由は➀か➂のどちらの理由が大きいのかについてもよく銀行と話を重ねることが必要になりますし、何よりも自身の業績改善が金利引き上げを抑制する最大のカードになることを認識しておいてください。