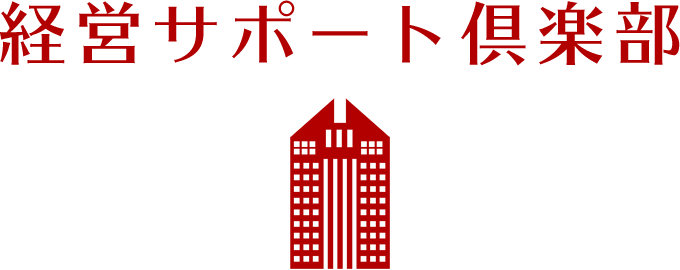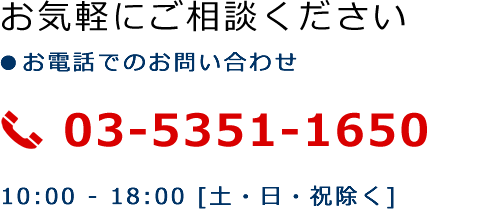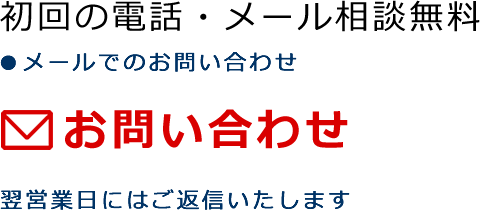経営サポート倶楽部
経営サポート倶楽部
【経営サポート倶楽部】7期目 第28回目のセミナーを行いました
2025/01/21
1月17日 今回は商工中金 本店営業部の方を講師にお招きして「商工中金とはどういった金融機関なのか」「融資スタンスはどうなのか」をテーマにお話しいただきました。
- 融資対象企業
「法人」のみの対象となり、事業規模は売上10億ほどが目安となるが、3億ほどの小規模クラスにも融資をしている。(ただし小規模といっても「持ち株会社」や「資産管理会社」もある) - 融資対象業種
「不動産売買」「不動産賃貸」「デベロッパー」への融資はかなり厳しく、ほとんどやっていない。
「製造業」や「運送業」への融資が多い - 新規取引ルート
「一見」で窓口に相談に来るのは基本NG(予約が必要)。取引のきっかけとしては「税理士からの紹介」「既存取引先」からの紹介が多い。→新規取引を希望する法人がいる場合は、皆さんからの紹介ルートが効果的。
商工中金として新規営業を飛び込み形式で行っているが、かなり対象を絞っている。 - 民業圧迫の考え方
他の取引金融機関の「融資シェア」はかなり見ている。他の金融機関の融資を「肩代わり」することはしない。
ただし、時間をかけて結果として「シェア逆転」はある。
特に「地銀」「信金」との関係は重要視しており、地銀や信金の融資シェアを取りにいくことは避けている。
(メガバンクには気にせず仕掛けていくことも多い)
→「部分最適」<「全体最適」の考えが信用しており、目先の自行のメリットよりも顧客の中長期的なメリット
は何なのか?を思考している(民間金融機関との違いがある) - メインバンクの地位の志向
基本的にはメインバンクを目指してはいないが、結果的にメインになることもある。シンジケートローンのアレンジャーもやる。 - 創業ステージへの融資
公庫と違って「創業融資」はやらない。ただし創業ステージでの「アーリー後期」(ベンチャーキャピタルからの出資を受けた後のステージ)への融資は積極的で専門部署(スタートアップ営業部)が担当する。 - 金融商品の対応
「金利デリバティブ(金利スワップなど)」「為替デリバティブ(クーポンスワップなど)」メガバンクがもっている商品は商工中金にもある。特にクーポンスワップ(輸入為替)はメガよりも小ロットでの対応が可能
トータルの感想としては
- 商工中金との取引メリットは他の銀行の安心感にある。つまり、民間金融機関の志向として商工中金が取引しているなら「ちゃんとした会社である」との認識があり、取引金融機関の中に商工中金を入れるのはメリットがある。
- 民間金融機関のような時代背景に左右されて支援スタンスが左右されにくい金融機関であり、腰を据えた取引関係が構築できるのがメリット
普段は、なかなか商工中金の方とは接点がない方も多く、非常に有意義な時間となりました。
※次回は4月18日に私が担当します。昨年に引き続き「事例研究」を予定しておりますので、是非ご参加ください!